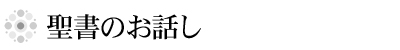「元気になりなさい(マタイ㊳)」
更新日:2024.12.9
マタイによる福音書第9章18-26節
小林克哉 牧師
少女であった娘の死に直面していた父親=指導者がいました。会堂司=宗教的な指導者で人々から尊敬され、ある意味、権力も富も名誉も手に入れていたのです。しかし愛する娘の死という現実を前にしては、それら手に入れたもの全てが意味をなさなかったのでした。わが子の死という現実、このような悲しみや嘆きがあるのが、わたしたちが生きている世界なのです。
この父親の祈りをイエスさまは聞かれます。「そこで、イエスは立ち上がり、彼について行かれた。弟子たちも一緒だった。」(19節)イエスさまは放っておかれません。すぐに立ち上がり、このいたたまれない出来事のただ中にいる者と共におられ、一緒に行ってくださるのです。そして弟子たちも一緒に行くのです。すなわち教会も、このイエスさまの伝道の業について行くのです。イエスさまがその人を救ってくださることを目撃し、そのために用いていただくのです。
ある牧師が、牧師として献身するきっかけの一つになった高校生のときの出来事について聞いたことがあります。教会学校でいっしょであった人だったそうですが、その出来事の少し前にある教会で洗礼を受けキリスト者になっていました。しかし、多くの人の命が奪われた不慮の事故で亡くなられたのです。同じ年齢でした。あまりにもいたたまれない出来事であり、この世界にはこんなに悲しく嘆かわしいことが起こるのだと、高校生ながらに思ったというのです。そして、神さまがおられるということ、イエスさまの十字架と復活により永遠の命が与えられることがどんなに大きなことかと思い、このことを伝えなければならないと思ったというのです。
「イエスは家の中に入り、少女の手をお取りになった。すると、少女は起き上がった。」(26節)「起き上がった」という時は、復活することを表すときにも使う言葉です。この少女は、そしてわたしたちもイエス・キリストの十字架により罪赦され、神の愛と恵みのご支配の中に置かれ、復活と永遠の救いの希望の中に生きる者とされ救われるのです。クリスマス伝道の時です。この救いを知った者として、悲しみと嘆きがあるこの世界の中を生き、福音を宣べ伝えていきたいと願います。アーメン
(2024年12月1日礼拝説教より)